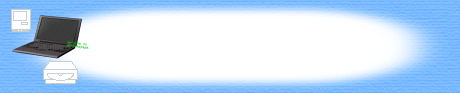|
|||||||
|
|||||||
| HOME > 2003年のコラム | |||||||
|
|
|||||||
| 世界にひとつだけの花 | |||||||
|
2003年も終わり、新しい年を迎える。 景気はまだまだだが、かすかに明るさも見えてきた気はする。2003年にも色々なヒット商品や流行が生まれたが、2004年はどんな時代になるだろうか。企業の浮沈も、要はいかにして時代に沿っていけるかということに尽きる。 歌の世界では、2003年の最大のヒット曲は「世界にひとつだけの花」だったようだ。SMAPはこう歌っている。 「ナンバーワンにならなくてもいい。もともと特別なオンリーワン」 「ぼくらは世界にひとつだけの花。ひとりひとり違う種を持つ。その花を咲かせることだけに一生懸命になればいい」 ・・この歌がなぜヒットしたかをこのごろよく考える。 |
|||||||
|
2003年12月29日
|
|||||||
| ニューヨークに雪が降る | |||||||
|
毎年この時期になると年末年始の工場の稼働状況が気になる。 いくら中小企業の事業主や上場会社のIR担当や営業マンが「忙しい」といっても、どうしても温度差や彼らなりの思惑を完全に拭うことはできないが、年末年始の工場の稼働状況はある意味で端的に受注状況を示唆している。 国内半導体メーカーの予定をみる限り、足元の受注は活況なようだ。 東芝は、フラッシュメモリの四日市工場が正月返上で稼働、LSI拠点の大分工場も2日間のみの休止にとどめる。NEC(NECエレクトロニクス)は滋賀工場(NEC関西)を1日のみの休日とするなど昨年より3日間も多く稼働させる。また昨年は1週間休んだ富士通でさえ(?)今年の休日は2日間のみにとどめるという。 あとは最終需要が好調で今の受注増をさらに牽引してくれることを望むばかりだが、週末ごとに大雪になっているNYが少し気がかりだ。 |
|||||||
|
2003年12月21日
|
|||||||
| 100分割より大切なもの | |||||||
|
先に株式の100分割を発表して話題になったエッジの堀江社長が、月刊誌「ビジスタ」10月号でその狙いを書いている。 既に知る人も多いかもしれないが紹介する。堀江氏は「(株価を数千円というレベルにすることで)多くの人に自社の株式を保有してほしかった」と語っている。そのことの株価への波及効果をここで問うつもりはない。ただ注目するのは、このように考える経営者がどれほどこれまでいただろうか、ということだ。 株価対策に苦慮する経営者はいただろう。しかし多くの人に自社株を保有してほしいという単純な発想は、従来の経営者には希薄だったのではないか。そしてその背後にあるのは、投機としての株式にとどまらない。そのことを含んだ株主と会社のありようだ。 100分割発表後のエッジの株価は迷走が続いている。堀江社長の理念は伝わっていないか、あるいは受け入れられていないかのどちらかだ。 堀江氏の考えに対する結果は、権利とりの今月末とか権利行使の来年2月とかいう水準ではなく、何年というスパンでいずれ出るだろう。 |
|||||||
|
2003年12月12日
|
|||||||
| 弱気は損気 | |||||||
|
半導体製造装置の中堅某社の役員と話をする機会があった。受注、受注残ともに確実にあがっており「下期は上期以上の業績になるのは間違いない」と語っていた。 先日発表になった日本半導体製造装置協会(SEAJ)の10月の日本製装置(日本メーカーがつくる半導体製造装置)の受注をみても、前年同期比倍増となっており、1453億円という金額は「ほぼ3年ぶりの高水準」なのだそうだ。 「しかし」である。件の役員は「下請けの外注先が増産投資を渋っている」ことも明かしていた。足元も受注は多くても増産投資をするまでの強気にはなれないところに傷の深さが窺える。不況期に積極投資をして成功した韓国サムスンの成功例は頭にあっても、実行は難しいようだ。 明るさのなかにある弱気が景気回復の腰折れを誘発しなければいいが・・。 |
|||||||
|
2003年12月1日
|
|||||||
| クリスマスには・・ | |||||||
|
米国のGDPは好調、9月中間の各社決算も概ね業績回復が確認され、大手銀行の決算にも明るさが見え始めた。 基調は悪くない。ファンダメンタルズで見れば、株価はこれから年末高に向かっても不思議はない。しかし一部のテクニカル論者に言わせると「まだ調整は不十分」なのだそうだ。 テクニカルを重視する人によれば、上昇も下落も波動があるが、下落波動はまだ終わっていないのだそうだ。では「その終わりはいつか?」と言うと、12月下旬で、平均株価でいうと9100〜9200円がめどという。 一笑に付したいが、先の下落局面を言い当てているだけに、こちらの笑顔も少しこわばる。 クリスマスには笑顔で過ごしたいが・・。 |
|||||||
|
2003年11月27日
|
|||||||
| 新しい経営哲学 | |||||||
|
エッジが株式分割を発表した。噂が根強くあったが、誰も1対100という比率は予測できなかっただろう。その効果には様々な議論があるが、背後にある経営哲学や信念は多くの企業のトップが見習っていいのではないか。 楽天の330億円を投じてのDLJディレクトSFG証券の買収、あるいはソニーのモデム無料配布キャンペーンも同様である。 成長性への疑問やその経営戦略を否定する声もあるのは事実だが、3社が提示している新しいビジネスモデルは、旧来にはないものだ。それを否定するのはたやすいが、いつの世でも時代を切り開くのは結局はこうした新しい考えではないだろうか。 |
|||||||
|
2003年11月22日
|
|||||||
| 秋の空気 | |||||||
|
にわかに株式市場に不透明感が強くなった。前回のコラムでも書いたが、テクニカル面から「調整入りは必至」と指摘していた声はともあれ当たったことになる。 ところで財務省が12日に発表した今年上半期(4〜9月)の対内対外証券投資状況によると、海外投資家の日本株投資は過去最高の買い越し(6兆8523億円)だったそうだ。ところが直近の外資系証券の動きをみると、10月第5週には852億円買い越したが、11月6日以降は5営業日連続で売りだしている。一部では、早くも「外国人が日本市場から逃げ出した」という声も出る始末だ。 実際のところ、海外の機関投資家が利益確定の売りを出していることは間違いない。そしてそれが下落要因のひとつになっていることも確かだ。 かろうじてそれを支えているのは国内の個人投資家か。何だか泣けてくる構図だ。日本の底力を見せてほしいが、秋のせいかため息ばかりが出る。 |
|||||||
|
2003年11月13日
|
|||||||
| 祭りの後 | |||||||
|
9日にいよいよ総選挙がある。このコラム執筆時点では無論結果は知る由もない。自民党圧勝という下馬評だったが、逆にこれがアナウンス効果で民主党が大躍進するという直前予想もあった。投票率などによっても大きく変化するだろう。 自民党が過半数を維持すれば国内外の投資家には安心感が広がるというのが通説だが、英国フィナンシャルタイムス紙が「2大政党の誕生は好ましいこと」と報じているように、単純に自民党が勝つことだけが市場の安定につながるとは言い切れない。 平均株価は4月末の底値から既に6カ月の上昇局面、この間の上昇率も5割弱にまで達した。テクニカルで市場を見る人に言わせると「調整は必至」な局面にきているそうだ。しかし米国株高や個別企業の業績安定からして、今回の上昇はまだまだ続くという声も多い。 いずれにしても「選挙までは動けない」という言い訳はもう通じない。いよいよ正念場に差し掛かっている。 |
|||||||
|
2003年11月8日
|
|||||||
| ソニーのアイデンティティー | |||||||
|
ソニーの経営説明会が10月28日に開かれた。そうなるだろうと思った通り、テレビなどメディアも新聞各紙もリストラに焦点をあてている。 確かに2万人の削減というのはインパクトがあり、見出しにもなりやすい。しかしソニーが会見で伝えたかったメッセージは、リストラによる経営体質の改善ではない。同日付の当サイト企業動向記事で詳細は述べているのでここでは会見の内容は繰り返さないが、出井会長の一言だけをあげておく。どのメディアもとりあげていないが、それは 「パソコンは一般ユーザーが気軽に使えるメディアとは言えなくなっている。トラックみたいなもので、気軽に呼んで使えるわけではない」 というものだ。 ソニーが目指すのは、テレビのようにスイッチを入れるだけでつながる新しい情報プラットフォームの構築だ。その壮大な夢がソニーのアイデンティティーだ。 |
|||||||
|
2003年11月1日
|
|||||||
| 旬 | |||||||
|
すっかり季節は秋めいてきた。だからというわけではないだろうが、どうも景況感は移ろいやすくなっている。 株式市場も、先週は週初めの20日月曜日には年初来高値を更新したが、翌日から下降し、23日には米国同時多発テロ以来の大幅な下げとなるなど上下に激しく揺れた。下落の要因は、1急騰の過熱感、2米国市場の停滞感、3円高圧力、4政局不安、に集約される。 10月最終週にどのような動きが待っているかは結局推測の域を出ないが、上記の4項はいずれも致命的とは思えない。したがって「下値は限定的だろうが、調整はやむなし」という声が多いようだ。しかし誰もが不安を抱えているのは事実だ。それは秋のせいばかりでなく、芥川龍之介ではないが「将来へのぼんやりとした不安」があるからだろう。 結局は理屈ではなく、その不安の多寡で市場の趨勢は決まる。理屈抜きに不安が増せばクラッシュもあるし、逆に理由なき高騰もそこから生まれる。 まあよい。見上げれば空は抜けるような秋の青空である。しっかりと見極め、旬のものを味わおう。 |
|||||||
|
2003年10月27日
|
|||||||
| ハリウッドレベル | |||||||
|
16日のタブロイド夕刊G紙の一面で「任天堂、バンダイを買収」と報じられた、何の会見通知も事前情報もなく,あわてたが、当の新聞を買い求めて見ると、中身の記事には「買収」の後に「計画」が入っているという笑えない笑い話だった。 事実関係としては同日任天堂も正式開示したが、機関投資家からの要請に応じてバンダイの発行済み株式の2.6%(同社10位の株主)を取得したというものだった。両社とも「それ以上のことはない」というコメントだが、件のG紙ではUFJ銀行出身のバンダイ高須社長の山科会長との確執も報じている(この話、確認はとっていません。念のため)。 思い起こせば、バンダイは97年にいったんセガと合併を決めたが、その後撤回している。そしてそのセガがサミーやナムコと経営統合でもめたのは記憶にも新しい。 それがゲーム業界の体質だと言われればそれまでだが、合併もその撤回もお手軽なのは、結婚、離婚が日常茶飯事なハリウッド並みか。 それはそれでいいが、せめて興行成績(業績)もそうあってほしいところだが・・。 |
|||||||
|
2003年10月18日
|
|||||||
| どこまで手ぬるいか? | |||||||
|
円高が景気と株価回復に大きな重しとなってきた。10日のニューヨーク市場では、一時108.28円とついに2000年11月中旬以来の高値まで上昇した。メリルリンチ証券では、ドルの長期下落傾向は始まったばかりとみており、レート予測を2004年3月末に1ドル104円、9月末は98円とみている。 電機大手では為替想定レートの見直しが相次いでいる。NECは120円を110円に、東芝は120円を115円に、キヤノンは118円を110円、三菱電機は120円を115円にそれぞれ変更した。 メリル証券の推測が当たるなら、上記各社の見直しはまだまだ手ぬるいということになる。 どこまで本当に手ぬるいかはまだわからないが、今月下旬から本格化する中間決算ではこうした為替見通しも今期業績予想に織り込まれていくことになる。 各社の手ぬるさを見極めることも投資家の重要なファクターとなる。 |
|||||||
|
2003年10月12日
|
|||||||
| 情熱のありか | |||||||
|
勝ち組として、デジカメやカメラ付携帯電話関連メーカーが挙げられて久しいが、このところパチンコ・パチスロ関連の各社からも明るい話を聞くようになった。 前期はワールドカップ開催に伴う自主規制もあり低迷していたため、「ある程度回復して当然」という要素はあるにせよ、回復の兆しを感じる。繁華街ではホールの改装も目にするようになり、機器メーカーばかりでなく、関連部品を手がけるところも受注は活性化している。 半面、ゲーム機は転換期に来ているようだ。9月中間決算で上場来初の赤字を計上する任天堂の岩田社長は、先に「ゲーム業界は発展か停滞かの岐路にさしかかっている」と危機感を感じさせる発言もしている。また某紙のアンケート調査では、ゲーム機ユーザーの過半数がゲームソフトが以前よりつまらなくなったとも答えていた。 かつて量販店に長蛇の列で並んでいたゲームソフトを買う人々の行列と、新装開店のパチンコ店に並ぶ人々の列が妙に重なって見えるのは気のせいだろうか。 ひとつ言えることは、その先にあるのが何であれ、行列に並ぶ人々の情熱だけはまだそこにあるということだ。その情熱がある限り、そこに需要はある。 |
|||||||
|
2003年10月6日
|
|||||||
| トロンに見た夢 | |||||||
|
日本が生んだ基本ソフト「トロン」とウインドウズのマイクロソフトが提携した。 かつていったんはパソコンの基本ソフトになりかけたトロンだが、政治的な日本の弱腰もあり、現在のマイクロソフトの独占状態を許した。 もしあのとき、日米経済摩擦のなかで日本がトロンで連合を組み、世界標準になしえていたら現在の世界情勢は変わっていた可能性さえある。少なくともマイクロソフトの天下はなかったし、米国が握っている世界の覇権も違っていただろう。日本の「失われた10年」もなかったかもしれない。 まあよい。過去を置こう。ともあれ、トロンの夢を捨てなかった東大坂村健教授の思いは今新たな道を開いた。トロンは日本を新たなステージに導くかもしれない。そして夢を捨てなかった坂村教授の気持ちも学びたい。 |
|||||||
|
2003年9月29日
|
|||||||
| ソニーの明日 | |||||||
|
評価は様々だろうが(現状では批判の方が多い?)、ソニーのコンセプトは比較的はっきりしている。 デジカメでは業界最高の800万画素の製品を、DVDレコーダでは325時間の録画が可能な250ギガ製品をそれぞれ投入した。さらにゲーム機は情報端末機器として今後位置づけていく構えだ。 頭記のデジカメは単価16万円だが、果たして1万9800円の機種より10倍価値があるかという疑問や、ゲーム機は単なるゲーム機でよいのではないか、という声もあがっている。 しかしそこがまさにソニーの意図するところなのだろう。価格競争ではなく、製品のクオリティと可能性を追及していこうという考え方がそこにはにじむ。 デフレの時代のなかでそれは異質であり、錯誤と批判されるのも確かに見当外れとは言いがたい。しかしそれこそソニーの戦略であり、言葉を変えれば自負でもあるのだ。 ソニーが復活するかどうかは、単なる一企業だけの問題ではない気がする。 |
|||||||
|
2003年9月22日
|
|||||||
| 一晩中踊り明かそう | |||||||
|
4月末からの株価上昇局面を、かつてのITバブルに重ね合わせて見る人が少なくない。ソフトバンクや光通信の最近の強さを見ると、余計にそう思う。 確かに、後からつけた理屈はいくらでも出せるが、それだけでこの急上昇は十二分に説明できない。理屈を超えた何かが背後に醸成されつつあると思わざるをえない。そしてそれがまさにバブルなのだろう。 しかし私はここでそれを戒めるつもりはない。むしろ、バブル歓迎である。萎縮している日本経済にはバブルが最良の薬だとさえ思う。 ただ、残念なことに我々の傷は深い。皆が臆病になっているのは確かだ。バブルはプチバブルで終わると言う人の根拠はそこにある。 そうかもしれない。そうかもしれないが、後で虚脱感が来るほどのバブルを望む気持ちもあるのは私だけだろうか・・。 |
|||||||
|
2003年9月14日
|
|||||||
| さんまの季節 | |||||||
|
早くも9月の中旬になる。まだまだ暑いが、ともあれ夏は終わった。いや、今年の夏はなかったとも言える。 冷夏に終わったことで、その景気への悪影響が懸念されている。確かに、過去の例から言っても猛暑の方が景気にプラスであることは間違いない。しかし本当にマイナスばかりだったのだろうか? 春先にかけて大きな懸念材料だった電力不足は、冷夏のおかげで無事に乗り切った。気を揉んでいた関係者にしてみれば、冷夏は神風のようなものだっただろう。産業界全体で考えても、もしかすると神風だったのかもしれない。 過日「デフレ基調には飽きてきた」という主旨のことを書いたが、そろそろ悲観論にも飽きてきた。 猛暑だったなら、政府が有効な経済策をとってきたなら、と憂いていても始まらない。冷夏も政府の無策も過ぎてしまったことだ。もしかすると冷夏でよかったのかもしれない。のんきな小泉さんでいいのかもしれない。 そう考えて、この秋はさんまでも堪能しよう。ちなみにさんまは、魚のさんまだ。まあのんきそうなさんまを見て笑って過ごすのも一興だが・・。 |
|||||||
|
2003年9月8日
|
|||||||
| このページのトップへ | |||||||